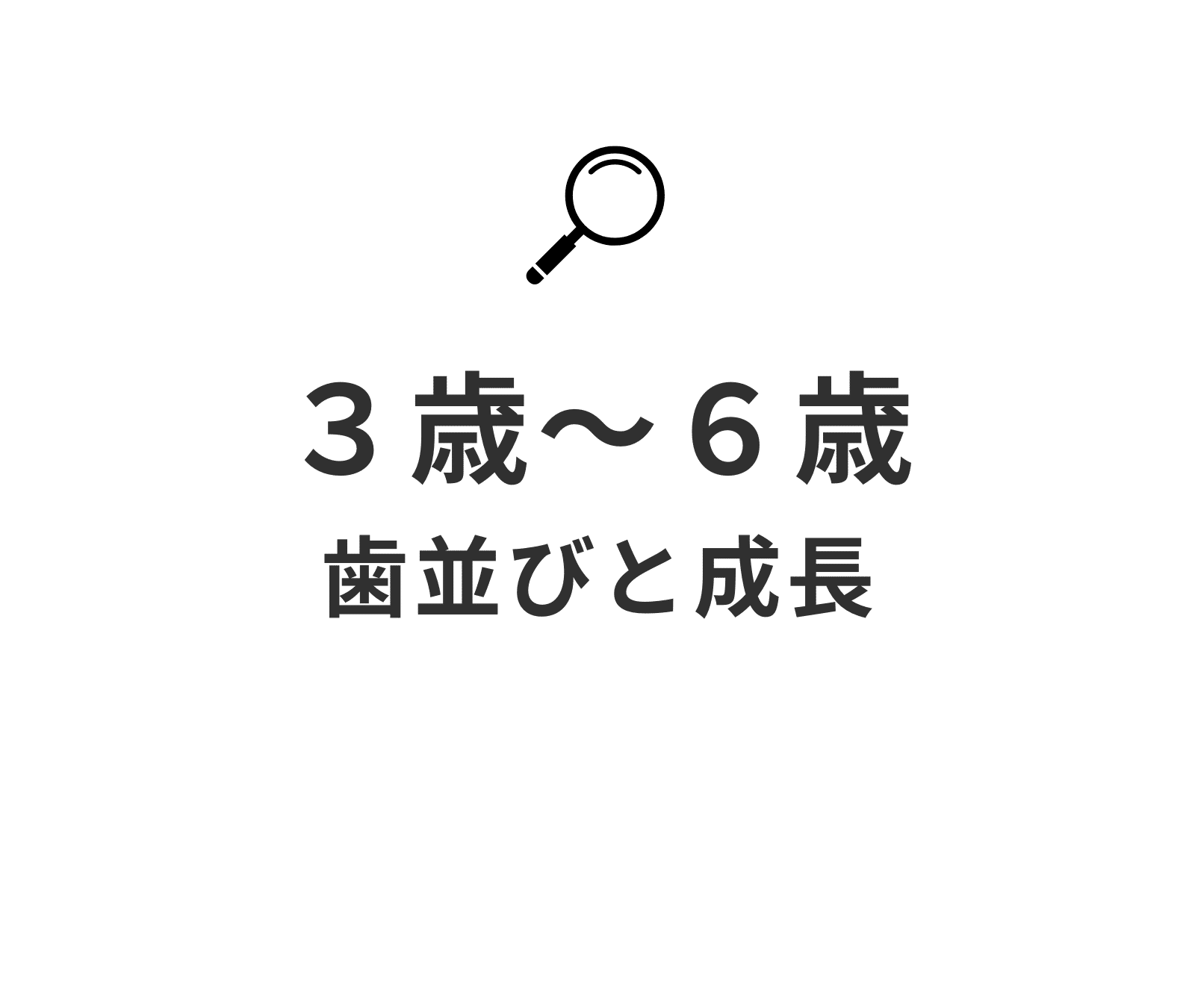

3〜6歳は、乳歯から永久歯へ移行が始まる「混合歯列期」の入り口です。6歳前後に生える「6歳臼歯」や前歯の生え替わりは、将来の噛み合わせの“基準”になります。この時期に適切な評価と必要なサポートを行うことで、将来の抜歯リスクや大掛かりな治療の可能性を低減し、自然で機能的な歯ならびを育てやすくなります。
このページで分かること
3〜6歳(乳歯列期):乳歯でも早期介入が必要なケース

この時期は指しゃぶりや口呼吸などの生活習慣を改善することが中心です。
- 受け口(反対咬合)や切端咬合がある場合は、この段階でかみ合わせを整えておくと、治療が非常にスムーズに進むケースが多いです。これらの不正咬合に関しては、後回しにすると年齢が上がるごとに治療計画が複雑化しやすいので、早期の対応が肝心です。
- 指しゃぶりや習癖が原因の出っ歯(上顎前突)や開咬(オープンバイト)も、この時期に対処しておくことで改善がスムーズになります。年齢が上がると治療の難易度が高くなる点には注意が必要です。
さらに、それ以外にも特定の症例によっては3歳ごろがベストな開始時期となる場合もあります。もし気になる症状があれば、3歳頃に一度複数の歯医者さんで歯並びについて相談しておくと安心です。
幼稚園・保育園児のうちに始めるメリット
・ 顎が最も柔軟な時期で、生活習慣改善に取り組みやすい
・ 個人差が大きいので、定期検診での経過観察が大切
3〜6歳の歯ならびと顎の成長(混合歯列期の入り口)
5〜6歳頃に最初の永久歯(6歳臼歯や前歯)が萌出し、歯ならび・噛み合わせの基準ができていきます。顎の骨格形成が活発なため、歯列の土台づくり(アーチ幅の確保、前後・左右バランスの調整、噛み合わせ誘導)がしやすい時期です。0〜3歳より将来像の予測が立てやすく、必要に応じて予防的な介入や生活習慣の是正を行うことで、不正咬合の進行を抑えやすくなります。
この年齢に多いお悩みと受診の目安
- 前歯がデコボコに生えてきた(叢生)
- 受け口(反対咬合)・出っ歯(上顎前突)・開咬(前歯が当たらない)
- 指しゃぶり/舌突出癖/口呼吸/お口ポカン/いびき・歯ぎしり
- 二重歯列(乳歯が残ったまま永久歯が後ろに生えた)
- 6歳臼歯の生え方が気になる、磨きにくい
受診の目安:半年に1回の定期検診を基本に、上記のサインがあれば早めの相談をおすすめします。
検査・通院頻度と、開始時期の考え方
- 検診頻度:目安は半年に1回。変化が大きい時期は短めの間隔をご案内することがあります。
- 早期開始のメリット:顎の成長を利用して土台を整えることで、将来的な抜歯の回避や治療期間の短縮が期待できます。
- 痛み:この年代は取り外し式装置の比率が高く、強い痛みは少なめ。初期の違和感は数日で慣れることが一般的です。
この年齢で選ぶことの多い装置・トレーニング
筋機能療法(MFT)
呼吸・舌・唇・頬などの口腔周囲筋の機能を整えるトレーニング。口呼吸・舌突出癖・嚥下の癖など、歯ならびを乱す要因に同時にアプローチします。筋機能療法(MFT)
取り外し式機能的装置(マウスピース系)
夜間+日中短時間の装着で、習癖の是正と歯列アーチの育成を目指します(例:トレーナー系装置、プレオルソ、マイオブレースなど)。装置名はお子さまの状態に合わせて選定します。インビザライン・ファースト(一期治療)
拡大床(床矯正)
上顎・下顎の側方不足に対し、歯列の幅をゆるやかに拡げることで、将来の永久歯の並ぶスペースを確保します。適応は診査診断に基づきます。拡大床(床矯正)
その他の選択肢
- 保隙装置(乳歯早期脱落時のスペース維持)
- 固定式装置(必要時):診断上、有利と判断される場合のみご提案
※適応・装置選択は個別診断で決定します。治療に伴うリスクや副作用も合わせてご確認ください。
症状別の考え方(簡易ガイド)
- 反対咬合(受け口) 前歯が逆に噛む/下顎が前に見えるタイプ。早期の噛み合わせ誘導や成長コントロールが有効な場合があります。 詳しく見る
- 上顎前突(出っ歯) 上の前歯が前方へ突出。口呼吸・舌癖も評価し、装置+MFTで総合的にアプローチ。 詳しく見る
- 開咬(前歯が咬み合わない) 前歯が当たらず隙間が空く。指しゃぶり・舌突出癖の改善と装置併用で機能と形の両面から対応。 詳しく見る
- 叢生(歯がガタガタ) スペース不足で歯が重なる状態。歯列アーチの育成や拡大、二期での精密矯正を視野に。 詳しく見る
- すきっ歯(空隙) 正中離開・歯間の隙間。上唇小帯・舌癖・歯サイズなど原因を評価して計画立案。 詳しく見る
- 過蓋咬合(噛み合わせが深い) 深く噛み込み、下の前歯が上顎歯ぐきに当たることも。咬合挙上・前後/垂直コントロールが鍵。 詳しく見る
治療の流れ(相談→検査→計画→装置)
- 初診相談:まずは電話カウンセリングで気になる点やご希望を伺います。院内相談では選択肢と概算をお伝えします。
- 資料採得・診断:写真・3Dスキャンなどで記録し、咬合関係と成長段階を評価します。
- 計画説明:装置の種類、装着時間、通院頻度、リスクと費用を個別にご説明。
- 初回装置型取り:初回の装置作成のための型取り(機種によりスキャンのみの場合あり)。
- 装置装着・使用指導:装着練習、清掃・保管の確認。紛失・破損時の対応もご案内。
- 定期通院:およそ4〜8週ごと(個人差あり)。経過に応じて調整します。
費用・期間の目安
治療内容により異なります。標準的な費用の目安は「矯正治療と費用」にまとめています。カード対応、医療費控除の考え方もご案内しています。期間は1年半〜2年程度が目安ですが、成長や症状により個人差があります。
園・学校生活とご家庭での工夫
- 装着時間:夜間+日中短時間(装置により異なる)。行事・運動時は外す運用も可能。
- 清掃:食事中は原則外し、食後のブラッシング→再装着を習慣化。
- 保管:ケース持参を徹底。紛失・破損時はまずご連絡を。
起こり得るリスク・副作用
装着初期の違和感・疼痛、装置の破損・紛失、歯肉炎やむし歯リスクの増加、歯根吸収や歯肉退縮、計画変更の可能性など。詳しくは「小児矯正のリスク・副作用と注意点」をご覧ください。気になる点は遠慮なくご相談ください。
関連症例
よくある質問(3〜6歳)
なぜ3〜6歳が重要なの?
A. 混合歯列期の入り口で顎の骨格形成が活発なため、歯列の土台づくりがしやすい時期です。早めの評価で予防的アプローチが可能になります。
5〜6歳の永久歯萌出は将来の歯ならびに影響する?
A. はい。6歳臼歯・前歯は噛み合わせの基準。アーチ幅やスペース不足があると不正咬合のリスクが上がります。
どのくらいの頻度で受診すべき?
A. 目安は半年に1回。変化が大きい時期や装置使用中は短めの間隔をご提案します。
永久歯が揃う前から始めるメリットは?
A. 顎の成長を利用して土台を整えられるため、将来の抜歯回避や期間短縮が期待できます。後戻りもしにくくなります。
3〜6歳の装置は痛い?
A. 取り外し式装置が主で、強い痛みは少なめ。違和感は数日で慣れることが多いです。
反対咬合は3歳からでも治療できる?
A. 症例により可能です。早期の噛み合わせ誘導が有効な場合があるため、気になればお早めにご相談ください。
6歳臼歯で注意することは?
A. 萌出初期は汚れが溜まりやすく、虫歯リスクが高い時期。位置・角度の異常(二重萌出やひっかかり等)にも注意し、定期チェックを受けましょう。
3〜6歳向けのおすすめ記事
- 子どもの指しゃぶり完全ガイド:原因・影響・対処法
- 子供の二重歯列(二枚歯)とは?
- お口ポカンは自然には治らない?原因と対策
- 子どもが寝ている時のすごい歯ぎしり 原因と対処法
- 子供の永久歯がギザギザ?原因と対処法
- 子供の矯正は痛いの?出やすいパターンと対処法
- 子供のマウスピース矯正:寝る時だけでも効果ある?
- 子どもの交叉咬合(クロスバイト)とは?原因と治療法
ご予約・お問い合わせ/アクセス 矯正治療と費用 装置・治療法から探す 症例一覧
